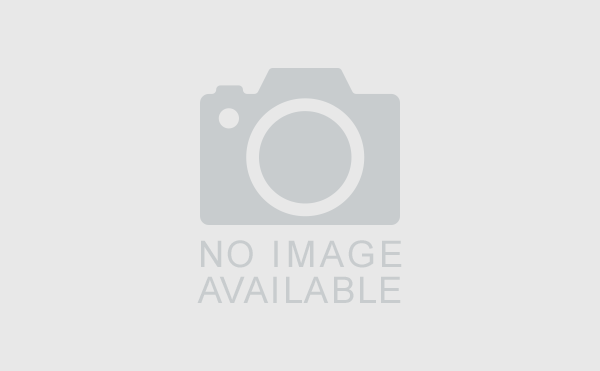2025年6月一般質問:大綱②循環型社会の形成について
6月議会の一般質問が終わりました。
1時間の質問持ち時間のなかで、一問一答方式を選び、毎回質問に臨んでいます。
一問一答の再質問前、1回目の質問と市の答弁を以下に書き出します。
※再質問部分については、任期中は市の公式HPの動画からご覧頂けます。
【林質問】
国連環境計画国際資源パネルによると、世界の天然資源の採取と加工が地球全体の温室効果ガス排出量の要因の55%以上、陸域の生物多様性の損失と水ストレスの要因の90%以上、粒子状物質による健康影響の最大40%を占め、気候変動を1.5度未満に抑制し生物多様性の損失を防ぐ目標をはるかに超過しています。私たちの存在基盤である環境や自然資本がゆらぐなかで、大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行型の線形経済から、資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済への移行と循環型社会の形成は、国際社会共通の差し迫った課題とされています。
国は、循環経済への移行は、環境課題の解決以外にも、輸入物価上昇の影響を抑え国際的な産業競争力や経済安全保障を強化するとともに、地域経済の活性化や地場産業の振興、地域課題の解決を実現し、持続可能な地域、さらには人類と地球全体の未来まで持続可能なものにするとしています。
循環型社会形成推進基本計画で地方公共団体が期待される役割は、地域の事業者や NPO・NGO 等による3R+Renewable に関する取組やモノの点検・リペア・交換・再使用・シェアリング等を行う新たなビジネスに対する支援、環境に配慮したグリーン購入・グリーン契約、 地産商品の推奨・情報提供、空家法に基づく空き家対策等、多岐にわたりますが、とくに重要と捉えたのは、市民、事業者、NPO・NGO 等のあらゆる主体間の連携・協働を促進するコーディネーターとなる役割です。
市においては、昭島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に基づき、発生抑制を基本に、市民・事業者と協働しての循環型社会の形成を目指して精力的な施策展開をされており、先日は「月刊廃棄物」6月号で、市のリユース食器貸出事業の紹介記事をみつけ、誇らしく思いました。さらなる取組みに期待して、質問いたします。
細目1 ごみ処理等について
一点目、今後の可燃ごみ処理について、方針決定の具体的期限を教えてください。また、市民が身近で廃棄後のごみ処理がみえることは重要です。自区内処理の原則にたつかお答えください。さらに、2022年、建設環境委員協議会で可燃ごみ処理施設整備計画策定基本調査が報告されていますが、循環型社会形成に繋がる処理方式を期待しており、方向性を教えてください。
二点目、循環型社会形成には、市民・事業者の協力が欠かせませんが、目指す循環型社会の姿とそこにいたる取り組みに対する共通理解が、大前提として必要です。どのような周知と、連携をしていますか。
【市長答弁】
私たちの社会は、今日まで大量生産、大量消費に支えられ、便利で豊かな生活を送る一方、地球上の限りある資源やエネルギーを消費することにより、天然資源の枯渇、資源採取に伴う自然破壊、廃棄物の大量発生など、地球規模での環境問題を引き起こしております。
特に近年、地球温暖化に起因する気候変動が気候危機とも称される中、脱炭素に本気で取り組まなければ私たちの未来はないと言われている状況になっております。
こうした中、環境の保全に配慮した循環型社会の実現が求められており、ごみ処理事業に関しましては、一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に掲げる「未来につなぐ循環型のまちづくり」を基本理念として、ごみの減量化・資源化、適正処理に積極的に取り組んでまいりました。
市民の皆様のご協力によるごみの分別化の徹底、事業者との連携によるリサイクルの推進など、ごみの減量化・資源化は着実に進んでおります。今後も更なる取り組みを進めてまいります。
また、ごみの適正処理に関しましては、清掃センターが本格稼働から30年を迎えておりますが、ごみの減量化により、現状2炉ある焼却炉を同時運転することなく交互に使用しており、また、必要な修繕を計画的に実施することで、安定稼働を図っております。今後の方針につきましては、ある一定の方向で検討を進めております。市内の状況や現況の社会情勢に鑑み、熟慮を重ねているところでもあります。引き続き、関係機関等との相談・調整を継続し、慎重に進めさせていただきます。
【環境部答弁】
ご質問の2点目、循環型社会形成についてのごみ処理等について答弁申し上げます。
はじめに、今後の可燃ごみ処理につきましては、現清掃センターについて、これまで複数回にわたる精密機能検査を実施し、令和16年度まで使用可能とする計画的な修繕を実施しながら、環境に十分配慮し、安定的な運営に努めております。
清掃センターの更新につきましては、これまでの調査・研究、関係機関等との相談・調整により処理方法の方針、及び施設規模や場所の選定等について、一定の進捗を見ている状況であります。加えて、廃棄物処理に係る新たな技術や施設の広域化・集約化の動向等を十分把握しながら、国や東京都、関係機関との相談、調整等を重ねている状況であります。
今後の見通しといたしましては、自区内処理の原則に立ちつつ、これまでに得られた情報・課題等の更新を行い、清掃センターの更新に係わる全ての関係者の皆様から、十分な御理解をいただくことを基本に、新たな手法に係る処理能力及び環境性、経済性等を具体的に確認し、方針決定に向け慎重に進めてまいりたいと考えております。
次に、市民・事業者との連携等についてであります。これまで、ごみの減量化を推進するため、企業と連携して様々な取組を実施してまいりました。近年では、令和6年度からサントリーホールディングス株式会社との協定によるペットボトルの水平リサイクル、フランスベッド株式会社との協定による羽毛布団のリサイクル、令和7年度からはHOYA株式会社アイケアカンパニーとの使い捨てコンタクトレンズ空ケースの回収、株式会社カインズとの使用済み園芸用土の回収等を開始し、循環型社会の形成に努めているところでございます。
これらの取組につきましては、広報あきしまやホームページ、年2回全戸配布しているリサイクル通信への掲載や、X、LINE、ごみ分別アプリ等SNSも活用し、広く周知を行い、利用の促進のほか、ごみ減量及びリサイクル意識の向上を図っております。今後も、市域全体の循環型社会形成の機運醸成につながるよう、周知啓発に努めてまいります。