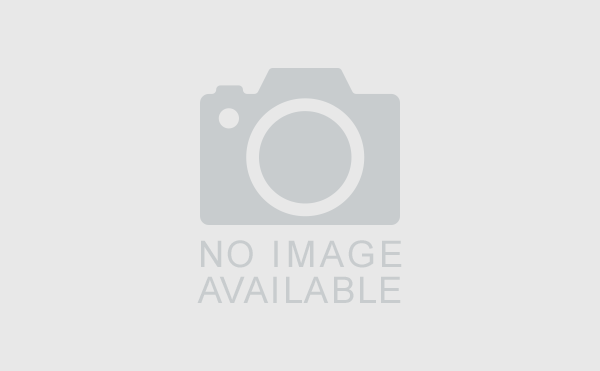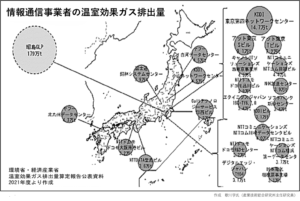昭島で子どもの権利に根ざした取り組みを
子どもの声に真摯に向き合う「子ども未来会議」を
生活者ネットワークがずっと訴え続けてきた、子ども会議・若者会議。本年、ようやく周年行事として「子ども未来会議」の予算がつきました。
今夏視察にいった大阪府泉南市の子ども会議では、参加募集のチラシ配布時から「こう配布すれば効果的だ」という子どもの声を反映、活動内容も毎年参加する子どもたちが決め、最終的に市長への報告が施策に活かされていました。
昭島市でも子ども未来会議において、施策に繋げることまで視野にいれる、施策にいれられないものもしっかりフィードバックして聞きっぱなしにしないことを求めました。市政への反映については真摯な対応を図るとの答弁があり、今後の実施に注目します。
一方、会議に参加しない子どもたちの声も工夫して聴取すべきですが、市では中神北側地区に新設予定の新畑公園の計画案を検討するにあたり、今夏、職員自ら児童センターに子どもたちの声を聞きにいき、計画案に反映しました。今後も、意見聴取や反映に庁内横断的に取り組むことを期待します。
子どもの権利の周知と子どもの権利条例制定を
本年、市では子ども施策の総合調整をするため、子ども未来課子ども政策係が新設されました。子どもの権利の理解浸透のため政策係中心に市職員の研修等実施すべきと質問。庁内に早速通信をだすなどの周知を検討、研修についても検討をすすめるとの答弁でした。
特に学校での、子ども当事者と学校関係者への周知や実践は重要です。「総合」の授業などで子ども参加を位置づけることを提案。教育課程は校長が編成するが、大変意義が大きく、各校における総合的な学習の時間が一層充実するよう、コミュニティスクールの取り組みとあわせて効果的な位置づけを考えるとの答弁でした。定期的な周知については、日頃からの人権教育とあわせて、子どもの権利についての学習機会もしっかりと研究・検討するとの答弁をえられました。確実な取り組みがなされるよう注視します。
相談・救済の仕組みとして、公正かつ中立的な立場であるオンブズパーソンについては過去質問した際には、既存の総合オンブズパーソン制度があるため、子どもオンブズパーソンの新設はしないとの答弁でした。各種媒体から一定の周知がなされていることはわかりましたが、子ども自身がわかるような周知を求めました。
全ての施策に子どもの権利が保障されるために、改めて「子どもの権利条例制定」を求めましたが、今後、子ども計画の策定予定があるなかで、子ども会議なども踏まえて検討するとの答弁。条例制定というプロセス自体が、私たちが子どもの権利と向き合う貴重な経験になるはずであり、制定すべきと今後も訴えていきます。