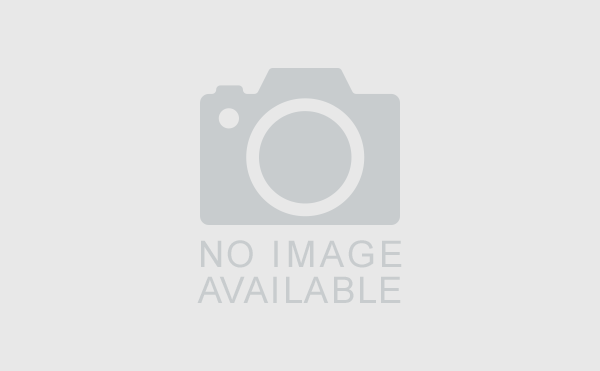2025年9月一般質問:大綱①誰もがいくつになっても住み慣れた地域でその人らしく暮らせる昭島へ
9月議会の一般質問が終わりました。
1時間の質問持ち時間のなかで、一問一答方式を選び、毎回質問に臨んでいます。
一問一答の再質問前、1回目の質問と市の答弁を以下に書き出します。
※再質問部分については、任期中は市の公式HPの動画からご覧頂けます。
【林質問】
ただいま議長の御指名を受けましたので、通告に従い、大綱2問の一般質問を始めさせていただきます。
大綱1 誰もがいくつになっても住み慣れた地域でその人らしく暮らせる昭島へ
細目1 昭島市地域福祉計画の諸施策について
すべての人が幸せに暮らせるよう社会全体で行う取り組みが福祉であり、地域福祉とは、地域で誰もが安心してその人らしい尊厳のある生活を送れるよう、様々な主体が協力しながら、地域社会の課題解決に取り組み、暮らしやすい地域をつくりあげることです。この地域福祉の推進については、社会福祉法第4条で、「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない」とされており、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が、「我が事」として参画し、人と人、人と資源や世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民ひとりひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が目指されています。
一方、ヤングケアラーなどのケアラー問題、ひきこもりや、80代の親が子どもを支える8050問題等々、制度の狭間にある新たな課題が次々生じており、いずれも深刻な状況です。また、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年を迎えましたが、本年上半期に自宅で亡くなった一人暮らしの暫定値が、4万913人、死亡推定日から警察による把握まで8日以上かかった孤立死が1万1,669人といずれも前年度比較で増加しており、2050年には全世帯の44.3%が単身世帯になるとの国の推計もあります。
孤独・孤立対策を検討する内閣府の「安心・つながりプロジェクトチーム」が7月に公表した報告書では、多数・多様な居場所が必要であり、その際には、担い手の「楽しいこと」「やりたいこと」であること、また「役割」や「出番」をつくりささえあい、肯定感・有用感を高められるような工夫や、地域活動と人材とのマッチング支援の重要性、さらに地方自治体の役割として支援や広報・啓発の強化など示されています。
一方、課題解決と別に、本来、地域で顔がみえ支えあう人間関係があることは幸せで豊かな状態のはずです。国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センターのいちプロジェクトに携わった内田 由紀子 京都大学教授 は、地域の幸福には、社会関係資本いわゆるソーシャル・キャピタルや、地域内でのサポートのやり取りなどが重要であることを見いだしました。ソーシャル・キャピタルとは、言い換えれば「つながりの力」であり、力をあわせての課題解決や、集まって話すことでのストレス解消、犯罪の減少などの効果があるとされており、ソーシャル・キャピタルが高い人ほど、そしてそれが高い地域に住んでいる人ほど、幸福感が高いことはさまざまな研究により示されているそうです。
思い返せば、私自身、核家族で子育てをするなかで、産後の孤立、あるいは、夏休みの居場所確保など課題が大きくなる度に、異世代交流サロンに助けられてきましたが、交流時間はかけがえないものでもありました。
子どもたちは私がしてあげられないような昔遊びや食体験をときにさせてもらい、何より自分たちを気にかけ手もかけてくれる多様な地域の大人にであい地域で育つ時間になりました。運営者については、もちろんご苦労もあったに違いないですが、子どもたちと過ごす時間は活気がでて笑顔も多く、はりあいや喜びもあられたのではないでしょうか。親の私は、世代が違う運営者に気負わず甘えられ、また大勢の大人の手があるためゆったりとした時間の流れのなかで子どもとコミュニケーションをとれ、育児や家事の知恵まで教えて頂き、世代を超えて繋がり、それぞれに豊かな時間を共有しながら、自然と支え合い課題解決までしている異世代交流やサロンの意義を実感する時間でもありました。
地域共生社会実現を掲げる第二期昭島市地域福祉計画では、「年齢、性別、障がいの有無などにかかわらず誰でも気軽に集まることのできるサロンなどの居場所や活動拠点づくりに務める」としていますが、この余裕のない時代でも、市民主体で多様なサロンがつくられ続けていることは誇るべきことです。
この大切な社会資源であるサロンをさらに活かす以外にも、重層的な取り組みを推進し、地域共生社会を実現する必要がありますが、行政・市民などそれぞれの役割も明確にしながら、ロードマップをもち取り組みしているか、また、実現予定時期と現在の達成状況をお答えください。
【市長答弁】
互いを尊重し、共に支え合い、助け合いながら生活を送ることができる「地域共生社会」の実現は、誰もが望むものであります。
人口減少、超高齢社会の到来や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、市民の皆様が生活を営む上での課題は、多様化・複雑化し、様々な分野の課題が絡み合い、深刻化、複合化しているものと受け止めております。
また、地域のつながりも希薄化が進み、支え合いの基盤が弱まってきており、生活に困難を抱えながらも誰にも相談できない、あるいは、適切な支援に結びつかないなど、課題がより深刻化するケースも増加しているものと認識いたすところであります。
国におきましても、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会「地域共生社会」をつくることを目指しております。
本市におきましても、こうした国の動きとも歩調を合わせ、地域福祉計画を策定し、地域共生社会の実現に向け、その取組を進めているところであります。
私といたしましても、目まぐるしく変化をする社会情勢下にあっても、市民の皆様の安全で安心な生活を守ることを第一とし、地域や関係機関とさらなる連携を図る中で、これまで以上に地域のつながりや支え合う仕組みづくりの構築と強化を図り、その実現に向けた取組を推進してまいります。
【保健福祉部長答弁】
御質問の1点目「誰もがいくつになっても住み慣れた地域でその人らしく暮らせる昭島へ」についてのうち、1点目の「昭島市地域福祉計画の諸施策について」御答弁申し上げます。
地域共生社会の実現予定時期と現在の達成状況についてでありますが、現行の地域福祉計画は、各種福祉関連計画との整合性と調和を図るとともに、福祉関連各分野において横断的に地域福祉を推進するため、理念と今後の方向性を定めた計画となっております。
また本計画は、令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とし、計画の進捗状況を評価するための基本指標、目標値を設定する中で、PDCAサイクルによる進行管理を行うこととしております。
現在は計画期間2年目となりますことから、福祉関連各分野別計画ごとの進捗管理をゆだねている現状にあります。
今後、計画期間の中間年である令和8年度に、分野別計画の進捗状況を踏まえた、評価・検証を行いたいと考えております。
いずれにいたしましても、本計画の目標年次である令和11年度に向け、「地域共生社会」の実現を目指して、市民、地域、関係機関・団体、行政が互いに協力し、それぞれの役割を果たしながら、一体となって包括的な支援体制の構築を進めてまいります。